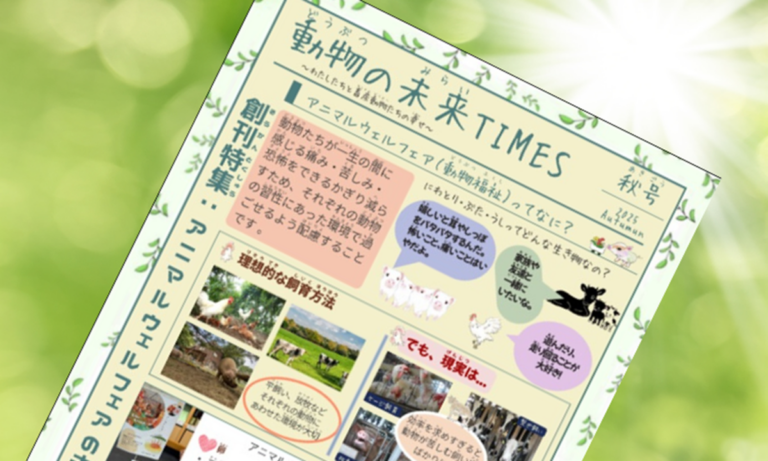OIE(世界動物保健機関・国際獣疫事務局)の陸生動物衛生規約の7章はアニマルウェルフェアについてですが、日本政府はこの作成に携わり税金を使っているにも関わらず、日本語訳を公開していません。OIEは獣医師が集まり科学的根拠を持って、また世界のレベルに合わせながら国際基準を作っており、畜産後進国である日本にとっては学ぶべきことが多数あります。
アニマルライツセンターは最低限このOIE動物福祉規約を守って欲しいと考えており、日本語訳を行い公開しています。
https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_aw_beef_catthe.htm
【アニマルライツセンター訳】2013年改定版
第7.9.章 アニマルウエルフェアと肉用牛生産方式
第 7.9.1.条 定義
肉牛の生産方式は、牛肉の消費を目的とした牛の繁殖、育成、仕上げ作業の一部または部を含む、すべての商業目的の牛の生産方式として定義される。
第7.9.2.条 適用範囲
この章では、子牛の誕生から仕上げに至るまでの肉牛生産方式の福祉を対象としている。子牛肉(veal)の生産は対象としていない。
第 7.9.3.条 商業目的の肉用牛生産方式
商業目的の肉用牛生産方式は以下を含む:
1.集約型
牛は舎飼いされ、餌、居住場所、水のように毎日、動物が基本的に必要としているものを、人間からの供給に完全に依存している。
2.放牧型
牛は屋外を自由に歩き回ることができ、摂食(放牧を通じて)、飲水、居住場所について、ある程度自律的な選択が可能である。
3.準集約型
牛は、上記集約型または放牧型を組み合わせた飼養方法である。気候や生理状態の変化に応じて二つの型のいずれかに変化する場合と、同時に二つの型を組み合わせた場合がある。
第7.9.4.条 肉用牛の福祉のための基準又は福祉の状態を測ることができるもの
以下の結果から(福祉の状態を)測り得る所見、特に動物の状態から測りうる所見は、アニマルウエルフェア(以下、動物福祉)の有用な指標となる。牛が管理されている様々な状況に応じて、これらの指標を用い、適切な閾値を適用するものとする。その際、生産方式の設計も考慮しなければならない。
1.行動
特定の行動は、動物福祉の問題を示唆していることがある。これら特定の行動には、摂食量の減退、呼吸促迫、息切れ(スコアにより評価)、常同症(同じ行動の繰り返し)、攻撃、沈鬱、その他の異常な行動が含まれる。
2.罹患率
疾患、跛行、術後合併症、負傷率を含む罹患率の一定の閾値を超える増加は、全群の動物福祉の状態を示す直接あるいは間接的な指標となりうる。疾患や症候群の病因を理解することは潜在的な動物福祉の問題を検出するために重要である。跛行スコアなどのスコアリングシステムは、追加的情報を提供することができる。
死後検査は、家畜の死因を確定するために有用である。臨床及び死後の病理学的特徴は疾病、傷害および動物福祉が損なわれたおそれがあるその他の問題の指標として利用可能である。
3.死亡率
死亡率は、罹患率と同様、動物福祉の状況の直接的または間接的な指標となりうる。生産方式に応じて、死亡率の推定値は死亡原因、時間的変化、空間的パターンを分析することによって得られる。死亡率は、日、月、年単位または生産サイクル中の主要な飼養管理活動を基準に、定期的に記録するものとする。
4.体重と身体の状態(栄養状態)の変化
成長期にある動物では、体重増加は、動物の健康と福祉の指標となりうる。貧弱な身体の状態と顕著な体重減少は、福祉が損なわれているかどうかの指標となり得る。
5.繁殖効率
繁殖効率は、動物の健康と福祉の状態の指標になり得る。悪い繁殖成績、例えば、以下の状態から、動物福祉の問題が示唆されることがある。
– 発情休止期または産後期間の延長
– 低受胎率
– 高流産率
– 高難産率
6.外貌
外貌は、動物の健康と福祉だけでなく、管理状況の指標となりうる。福祉の問題が示唆され得る外貌所見は次のとおり。
– 外部寄生虫の有無
– 異常な被毛の色調または質感、または糞、泥又は汚物による過度な汚れ
– 脱水
– 衰弱
7.取り扱い時の反応
不適切な取り扱いは、牛に恐怖と苦痛を引き起こすことがある。以下が指標に含まれうる。
– 保定枠または誘導路(枠)を出る早さ
– 保定枠内または誘導路における行動スコア
– 滑ったまたは転倒した動物の割合
– 電気式の追い棒で移動させた動物の割合
– 囲いや門にぶつかった動物の割合
– 管理中に負傷(角、肢の損傷、裂傷など)した動物の割合
– 保定中に声を上げた動物の割合
8.通常の管理処置に起因する合併症
肉用牛の生産効率を向上し、管理を容易にし、人の安全と動物福祉を向上するため、外科的および非外科的処置が一般的に行われる。しかし、これらの処置が正しく施術されない場合、動物の福祉が損なわれる可能性がある。このような問題の指標には以下が含まれうる。
– 術後の感染や腫脹
– ハエ蛆症
– 死亡率
第 7.9.5.条 推奨事項
各推奨事項には、第7.9.4 条に記した福祉の状態を測り得る所見のうち関連するもののリストが含まれている。このリストは、他で必要に応じて用いられている評価基準を否定するものではない。
1. 防疫措置と動物衛生
a) 防疫措置と疾病予防
防疫措置とは、牛群を特定の健康状態に維持し、感染性病原体の侵入や拡散を防ぐために計画された一連の措置を意味する。
防疫措置の計画は、望ましい牛群の健康状態や現在の疾病リスクに応じて、かつOIEリスト疾病については陸生コードの関連する推奨事項に従って設計、導入するものとする。
防疫措置の計画は、病原体拡散の主要な汚染源と感染経路の制御に対処するものとする。
i) 牛
ii) その他の動物
iii) 人
iv) 機材器具
v) 車両
vi) 空気
vii) 水の供給
viii) 飼料
(結果から)福祉の状態を測り得る所見:罹患率、死亡率、繁殖効率、体重および身体状態の変化
b) 動物の健康管理
動物の健康管理とは、牛群の身体的又は行動上の健康と福祉を最適化するために計画したシステムを意味し、疾病、怪我、死亡率、治療の記録を適切に織り交ぜた、疾病の予防、治療及び管理並びに牛群の状態を含む。
疾病の予防と治療のための効果的なプログラムが存在し、それは資格を持つ獣医師によって適切に作られたプログラムと整合するものとする。
牛の管理責任者は、摂食・摂水量の減少、体重と身体状態の変化、行動の変化や外貌の異常などの、体調不良や苦痛の徴候に注意するものとする。
身体や心を患っている危険性が高い牛は、動物取扱者によるより頻繁な調査が必要となる。動物取扱者が体調不良や苦痛の原因を取り除くことができなかったり、リストされた報告義務疾病の存在を疑う場合には、獣医師やその他の資格を持つアドバイザーなど、訓練と経験を有する者の助言を受けるものとする。
牛への予防接種及びその他の治療は、手順を熟知した者から、獣医または他の専門家の助言に基づいて実施するものとする。
動物取扱者は、歩行できない牛を認識し扱うための経験を持つべきである。彼らには慢性的な病気や怪我をした牛を管理する経験があるものとする。
歩行できない牛は、水は常に、餌も一日一回提供される状態にし、治療または診断のため絶対的に必要でない限りは輸送または移動しないものとする。移動は引きずったり、過度に持ち上げない方法で慎重に行うものとする。
治療が試みられた時、補助なしで立ち上がれず摂飲食を拒否し回復の見込みがない牛は、第7.5 章にしたがって人道的に殺処分するものとする。
福祉の状態を測り得る所見:罹患率、死亡率、繁殖効率、行動、外貌並びに体重及び身体の状態の変化。
2.環境
a)温度環境
牛は、特に予想される状況に対して適切な品種が選択された場合、広い範囲の温度環境に適応できるが、天候の急激な変動は暑熱または寒冷ストレスを引き起こすことがある。
i) 暑熱ストレス
牛への暑熱ストレスの危険性は、気温、相対湿度、風速といった環境要因と、品種、年齢、身体の状態、代謝率と被毛の色と密度いった動物側の要因によって影響を受ける。
動物取扱者は、暑熱ストレスが牛に与える危険性を認識できるものとする。暑熱ストレスを引き起こすと予想される条件のときには牛を動かす必要がある日常的活動は中止するものとする。暑熱ストレスの危険性が非常に高いレベルに達した場合、動物取扱者は、飼養密度の低減、日陰の提供、飲用水への自由なアクセス及び被毛に浸透する散水利用による冷却の提供を含む緊急行動計画を定めるものとする。
福祉の状態を測り得る所見:息切れスコアと呼吸率を含む行動、罹患率、死亡率
ii) 寒冷ストレス
牛、特に新生子牛や若い牛、そのほか生理学的に損傷した牛で、その福祉に重大な危険性を生む恐れがある場合、極端な気象条件からの保護を提供するものとする。こうした保護は、自然または人工的なシェルターによって達成することができる。
動物取扱者は、牛が寒冷ストレス時に適切に飲水・摂食できるようにするものとする。。極端に寒い気象状況の間、動物取扱者は、牛に退避場所、適切な餌や水を提供するために、緊急時行動計画を策定するものとする。
福祉の状態を測り得る所見:死亡率、外貌、異常な姿勢、震えと密集を含む行動。
b)照明
自然光が当たらない屋内で飼育されている牛にも、自然な行動パターンを促し、動物の適切な観察が可能となるよう、健康と福祉に十分な自然周期に従った補助照明を提供する必要がある。
福祉の状態を測り得る所見:行動、罹患率、外貌。
c)空気の質
良質の空気は、牛の健康と福祉にとって重要な要素である。空気の質は、気体、塵や微生物などの構成要素の影響を受け、特に集約型生産方式においては、管理方法に大きな影響を受ける。空気の構成要素は、飼養密度、牛の大きさ、床、寝床、廃棄物管理、建物の設計と換気システムによって影響を受ける。
適切な換気は、牛の効果的な放熱のために重要であり、アンモニアや排泄ガスの蓄積を防止する。空気の質の悪さと不十分な換気は、呼吸の不快感や疾病の要因となる。閉鎖環境のアンモニア濃度は25 ppm を超えないものとする。
福祉の状態を測り得る所見:罹患率、行動、死亡率、体重及び身体の状態の変化。
d)騒音
牛は、異なるレベルとタイプの騒音に適応可能である。しかし、突然のまたは大きな音に牛を暴露することは、ストレスと恐怖反応(例えば暴走)を防止するために可能な限り少なくすものとする。換気ファン、給餌機またはその他の屋内外の機器は、騒音が最小限となるように製造、設置、運用、維持するものとする。
福祉の状態を測り得る所見:行動。
e)栄養
肉用牛の栄養学的要求量はすでに明らかになっている。飼料中のエネルギー、タンパク質、ミネラルとビタミンは、成長、飼料効率、繁殖効率、体型を決定する主要要因である。
牛には、生理的欲求を満たす適切な質と量のバランスのとれた栄養を提供するものとする。牛が放牧型生産方式におかれている場合、短期間極端な気候に暴露することによっても、毎日生理的に必要な栄養が取れない恐れがある。そうした場合で福祉の状態が危機にある場合、動物取扱者は、栄養低下期間が長期化しないよう、緩和策をとるべきである。
動物取扱者は、牛の適切な身体の状態について十分な知識を持っている必要があり、身体の状態が許容範囲外とならないようにするものとする。飼料の補充がない場合、屠畜、販売、移転または安楽死を含め、飢餓を避ける手順を踏むものとする。
飼料および飼料原料は、必要な栄養を満たすために十分な品質のものとする。適切と考えられる場合は、動物の健康に影響を与えるような物質が含まれていないか、飼料および飼料原料を検査するものとする。
集約型生産方式における牛は、一般的に穀物(トウモロコシ、マイロ、大麦、穀物副産物)の割合が高く、粗飼料(干し草、わら、サイレージ、さやなど)の割合が低い飼料を摂っている。仕上げ中の牛で粗飼料が不足すると、舌遊びといった異常行動を助長することになる。飼料中の穀物割合が増加すると、消化異常のリスクは相対的に増加する。動物取扱者は、牛の大きさ、年齢、気候、飼料組成、突然の餌の変更が、消化不良やその他の悪影響(アシドーシス、鼓張症、肝膿瘍、蹄葉炎)を起こすことを理解するものとする。生産者は必要に応じて、牛の栄養の専門家に飼料の配合や給餌法に関する助言を求めるものとする。
生産者は、集約型または放牧型生産方式で発生しうる、地域特有の微量栄養素欠乏症または過多に精通し、必要に応じて、適切に補助栄養を与えるものとする。
すべての牛は、生理学的要求量を満たし、かつ健康に有害な汚染物質を含まない口当たりのいい水をいつでも十分に取ることができなければならない。
福祉の状態を測り得る所見:死亡率、罹患率、行動、体重及び身体状態の変化、繁殖効率。
f)床、寝床、休息場所の表面と屋外飼養場所
すべての生産方式において、牛には水はけがよく快適な休息場所が必要である。群内のすべての牛が同時に横臥し、休息するのに十分なスペースを確保するものとする。
集約型生産方式における牛房の床の管理は、牛の福祉に大きな影響を与える可能性がある。例えば、過度に水及び便が蓄積するといった休息に適さない場所がある場合は、(牛が)不快になるほど深くならないようにし、牛が使用可能な領域の計算に入れないものとする。
牛房の傾きは、飼い葉桶からの排水を可能にし、牛房内に水が過度にたまらないように維持するものとする。
牛房は、きれいな環境が維持されるように、最低限生産サイクルごとに一回洗浄するものとする。
牛がすのこの床の上で飼育されている場合、すのこと間隙の幅は、怪我を防ぐため、牛の蹄の大きさにあわせた適切なものを使用するものとする。すのこの床の上で飼われている牛には、可能な限り、寝床を確保しなければならない。藁またはその他の寝床を使う場合、乾燥していて牛が横たわるのに快適な環境に維持するものとする。
コンクリート製の通路の表面は溝を掘るか適当な凹凸構造とし、牛に適切な足場を提供するものとする。
福祉の状態を測り得る所見:罹患率(例えば跛行、褥瘡)、行動、体重及び身体の状態の変化、および外貌。
g)社会的な環境(動物同士の群内環境)
牛を管理する際、動物同士の群内環境は、特に集約型生産方式において、動物福祉に影響するため、これを考慮するもとする。問題となるのは次のようなものである:闘争活動及び乗駕、未経産雌牛と去勢雄牛の混合、異なる大きさや年齢の牛の同じ牛房内での給餌、高い飼養密度、不十分な餌場のスペース、不十分な水へのアクセス、種雄牛の混合。
すべての生産方式において牛の管理には、群内の動物同士の社会的相互作用を考慮するものとする。動物取扱者は、群内の優劣が群によって異なることを理解し、いじめや過度の乗駕の証拠から、例えば、群内で、極度の老若、大小などリスクが高い動物に注目するものとする。動物取扱者は、特に群を混合した後、動物間の敵対的な緊張関係が増すおそれがあることを理解するものとする。過度の闘争活動や乗駕によって苦しんでいる牛は、グループから除かれるものとする。
怪我をする危険性があるので、角のある牛とない牛は混ぜないものとする。
適切な囲い込みによって、牛の不適切な混合によって生じる可能性のある動物福祉の問題を最小限に抑えるものとする。
福祉の状態を測り得る所見:行動、物理的な外観、体重および身体の状態の変化、罹患率および死亡率。
h) 飼養密度
高い飼養密度は怪我の発生を増やし、成長率、飼料効率および、例えば運動、休息、摂食、摂水といった行動に悪影響を与える可能性がある。
飼養密度は、混雑によって牛の正常な行動に悪影響を与えないよう管理するものとする。これには、怪我の恐れなく自由に横臥できること、囲いの中を自由に移動し餌や水を取ることができることを含む。飼養密度は体重増加や横になっている時間が、混雑によって悪影響を受けないよう管理するものとする。異常行動が見られる場合は、飼養密度を下げるといった対策を取るものとする。
放牧的な生産方式では、飼養密度は、牛の飼料供給可能量に合わせるものとする。
福祉の状態を測り得る所見:行動、罹患率、死亡率、体重および身体の状態の変化、外貌。
i) 外敵からの保護
牛は、捕食者から可能な限り保護されるものとする。
福祉の状態を測り得る所見:死亡率、罹患率(負傷率)、行動、外貌。
3.管理
a) 遺伝的選抜
特定の場所や生産方式に適した品種や亜種を選ぶ場合には、生産性に加えて、福祉と健康状態を考慮するものとする。例として、必要な栄養状態の維持、外部寄生虫への抵抗性や暑熱の許容範囲がある。
品種内の個々の動物は、動物の健康と福祉にとって遺伝的によりすぐれた子孫を残すよう選抜できる。例として、母性本能、分娩の容易さ、出生体重、泌乳能力、体型と気質がある。
福祉の状態を測り得る所見:罹患率、死亡率、行動、外貌、繁殖効率。
b)繁殖管理
難産は、肉牛の福祉を損なうおそれがある。分娩時の母牛と子牛両方の健康と福祉を確保するため、未経産牛は十分に性成熟するまで繁殖に供さないものとする。種雄牛は、子牛の大きさに与える遺伝的影響が高く、分娩の難易度に有意に影響する可能性がある。種雄牛選択には雌牛の成熟度や大きさを考慮する必要がある。経産牛、未経産牛とも母牛と子牛の福祉を損なうリスクが高まるような方法で、移植や受精をおこなわないものとする。
妊娠中の雌牛は、太りすぎたり痩せすぎたりしないよう管理するものとする。。過度の肥満は難産のリスクを増やし、太りすぎ、痩せすぎとも妊娠後期または分娩後の代謝性疾患のリスクを高める。
可能であれば出産が近づいた妊娠牛は観察下におくものとする。分娩に関する問題が起こった動物は、可能な限り早期に、能力のある者が介助するものとする。
福祉の状態を測り得る所見:罹患率(難産の割合)、死亡率(母牛と子牛)、繁殖効率
c)初乳
初乳から十分な免疫を得られるかどうかは一般的に、摂取した初乳の量と質、そして出産後どれくらい早く子牛が初乳を受けるかに依存する。
可能であれば、動物取扱者は子牛が生後24 時間以内に十分な初乳を受け取れるようにするものとする。
福祉の状態を測り得る所見:死亡率、罹患率、体重の変化。
d)離乳
本章では離乳とは、子牛の餌を乳ベースのものから線維状のものへ移行すること意味する。肉牛の生産方式では、離乳は子牛期のストレスとなりえる。
子牛の離乳は、反芻動物の消化の仕組みが、成長と福祉を維持するために十分に発達してから行うべきである。
肉牛の生産方式では様々な離乳方法が用いられる。これらには強制離乳、柵による分離、哺乳を抑制するために子牛の鼻に器具を装着する方法が含まれる。
強制離乳の後、移動のような追加的なストレスを伴う場合には、牛の罹患率が上昇するおそれがあることから細心の注意を払うものとする。
肉牛生産者は、必要に応じて、牛の種類と生産方式に応じた最も適切な離乳時期と方法に関する専門的な助言を求めるものとする。
福祉の状態を測り得る所見:罹患率、死亡率、行動、外貌、体重および身体の状態の変化。
e)痛みを伴う処置の手順
牛には、生産効率、動物の健康と快適性、人間の安全性の理由から、痛みを伴う可能性のある処置が日常的に行われている。これらの処置は、動物に対する苦痛やストレスを最小限にするよう施術する必要がある。これらの処置は、できるだけ若いうちに実施するか、獣医師の監督や助言に基づいて鎮静または麻酔下で実施するものとする。
動物福祉を向上させるための将来的な選択肢としては、管理戦略によってこうした処置を不要とする、処置を必要としない牛を育種する、動物に快適性を増すことが知られている非外科的代替手段で置き換える、といったことが考えられる。
痛みを伴う処置の例:去勢、除角、卵巣摘出(spaying)、断尾、個体標識。
i) 去勢
肉牛の去勢は、動物間の争いを減らし、人間の安全性を向上させ、群れの中で不必要な妊娠を回避し、生産効率を高めるため、多くの生産方式で実施されている。
生産者は、肉牛を去勢する必要がある場合、牛の種類と生産方式に応じて最適な方法と時機について、獣医師から指導を受けるものとする。
肉牛で使用されている去勢の方法は、精巣の外科的な除去、虚血法、及び精索の破壊や切断が含まれる。
牛はできれば3 ヶ月齢より前に、またはこの年齢を超えて最初に飼養する機会に、動物に最小限の痛みや苦痛を伴う方法で去勢するものとする。
生産者は、特に高齢の動物の去勢の際、鎮静または麻酔の利用可能性や妥当性について獣医師から指導を受けるものとする。
肉牛の去勢を行う技術者は、用いる処置について訓練を受けて適切な能力を有し、合併症の徴候を認識できるものとする
ii) 除角(角芽の除去を含む)
肉牛は、怪我や皮革の損傷を減らし、人間の安全性を向上し、施設の破損を減らし、輸送と取り扱いを容易にするため、一般的に除角される。生産方式に応じて実用的かつ適切な場合、除角より、角のない牛を選抜する方が望ましい。
生産者は、肉牛を除角する必要がある場合、牛の種類と生産方式に応じて最適な方法と時機について獣医顧問(アドバイザー)から指導を求めるものとする。
牛は、実用的な場合、角が発達初期の蕾の段階、またはこの年齢を超えて最初に飼養する機会に除角するものとする。これは角の発達段階において角芽の状態であれば、組織的外傷を最小限にでき、角が頭骨に接していないからである。
発達初期における除角の方法には、刃物による角芽の除去、熱による角芽の焼灼、角芽焼灼のための薬剤塗布を含む。角の発達が始まった後の方法としては、頭蓋骨に近い基部で切削または鋸によって角を除去する方法がある。
生産者は、特に年を取って角が成長した牛について、鎮静または麻酔の利用可能性や妥当性について獣医師に指導を求めるものとする。
肉用牛の除角を行う技術者は、用いる処置について訓練を受けて適切な能力を有し、合併症の徴候を認識できるものとする。
iii) 卵巣摘出(Spaying)
未経産牛の卵巣摘出は、放牧環境下で不必要な妊娠を防ぐために必要となることがある。外科的卵巣摘出は、獣医師や高度な訓練を受けた技術者が行なうものとする。生産者は、卵巣摘出に際して、鎮静または麻酔の利用可能性や当性について獣医師に指導を求めるものとする。鎮痛または麻酔の使用が奨励されるものとする。
iv) 断尾
断尾は、舎飼い環境下で尾の先端の壊死を防ぐために、行われてきた。一頭当たりのスペースを増やし、床敷きを適切にすることで、尾の先端の壊死を防ぐ効果があるとの研究成果がある。従って、生産者に対して肉牛の断尾は推奨できない。
v)個体標識
耳標装着、耳刻、入墨、凍結烙印および無線周波数識別装置(RFID)は、動物福祉の観点から、恒久的識別手段として好ましい方法である。しかし、焼きごてによる烙印が必要とされたり、これが唯一実用的で恒久的な肉牛の標識方法である場合がある。烙印する場合は、迅速に、巧妙に、適切な器具を用いて実施るものとする。個体標識の方式は、第4.1 章に即して導入するものとする。
福祉の状態を測り得る所見:術後合併症率、罹患率、行動、外貌、体重および身体の状態の変化。
f)取り扱いと検査
肉牛は、生産方式並びに健康と快適性を損なうリスクに応じて適切な間隔で検査するものとする。集約型生産方式では、少なくとも一日一回、牛を観察するものとする。より頻繁な観察が動物を利する場合がある。例えば、新生子牛、妊娠後期の牛、離乳したばかりの子牛、環境ストレスを経験した牛、痛みを伴う管理処置や獣医の外科的処置を受けた後の牛。
動物取扱者は、肉牛の健康、病気や快適性に関する臨床的徴候に気づく能力があるものとする。牛の健康と快適性を適切に確保するため、十分な数の動物取扱者がいるものとする。
病気や怪我がみつかった牛は、できるだけ早い機会に有能で訓練された動物取扱者によって適切に処置されるものとする。動物取扱者が適切に処置できない場合は、獣医による治療がなされるものとする。
予後不良で回復の見込みがほとんどないとみられる動物は、できるだけ早く安楽死させるものとする。安楽死法については第7.6.5 条を参照。
牛の扱いについての推奨事項は第7.5 章にも記載されている。
肉牛は、放牧的な状態から管理施設に集める場合、静かにそして冷静に、最も遅い動物の歩調に合わせて移動させるものとする。気象条件を考慮し、牛を過度に高温または低温の状況下に集めてはいけないものとする。牛に苦痛まで引き起こしてはいけないものとする。牛を集め、取扱うことがストレスを引き起こす可能性が高い場合は、一度に複数の管理処置を組み合わせることを避けるよう考慮するものとする。取扱い自体がストレスとならない場合でも、複数の処置の継続によりストレスが追加されないよう、管理処置は、時間をかけて段階的に実施するものとする。
牛を集める際、適切に訓練された犬は、効果的な補助手段となる。牛は異なる視覚的な環境に適応可能である。しかし、牛を突然または持続的に移動させたり、視覚的に大きく異なる環境にさらすことは、ストレスや恐怖に対する反応を防止するために可能な限り最小限にするものとする。
電気麻酔(Electroimmobilisation)は使用してはならないものとする。
福祉の状態を測り得る所見:取扱いに対する反応、罹患率、死亡率、行動、繁殖効率、体重および身体の状態の変化。
g)人材育成
肉牛を担当するすべての人々は、その責任に応じた能力を持つ必要があり、牛の飼育、行動、防疫措置、病気の一般的な徴候、ストレス、痛み、不快感といった動物福祉が損なわれている指標やその軽減法について理解するものとする。
こうした能力は、正式な訓練または実際の経験を通して得ることができる。
福祉の状態を測り得る所見:取扱いに対する反応、罹患率、死亡率、行動、繁殖効率、体重および身体の状態の変化。
h) 緊急時の計画
肉牛の生産者は、停電、断水や飼料の供給停止が動物福祉を脅かすことが想定される場合、これらの供給体制の停止を補填するための緊急時対応(危機管理)計画を立てておくものとする。これらの計画には、誤動作を検出するための警報器、非常用発電機、機器メンテナンス業者の確保、農場での貯水や水の運搬サービスの確保、農場での餌の貯蔵や飼料代替供給先の備えが含まれる。
熱ストレス、干ばつ、吹雪、火事や洪水といった自然災害や極端な気候条件などの影響を最小限に軽減する計画が整っているものとする。病気や怪我をした牛の安楽死の手順は、緊急時行動計画の一部であるものとする。干ばつ時には、動物管理に関する決定は可能な限り早期に行い、牛の頭数を減らすことも考慮するものとする。緊急時対応計画は、国の事業や獣医サービスの勧告に整合した疾病発生時の農場管理計画を含むものとする。
i) (農場の)場所、建造物、設備
肉牛の農場は、牛の健康、快適性および生産性に資する適切な場所に設営されるものとする。
肉牛のためのすべての施設は、牛の快適性を損なう恐れを最小限に抑えるよう設置、維持、運用されるものとする。
肉牛を取扱い保定するための設備は、傷、痛みや苦痛を最小現にする方法でのみ使用するものとする。
集約型または放牧型生産方式で飼育されている牛には、快適で、動物同士の群内環境に適切なスペースを提供するものとする。
繋ぎ飼いの牛は、最低限、横臥できなければならず、屋外で繋留される場合は、転回及び歩行(turn around and walk)できるものとする。
集約的生産方式において餌場は、牛が適切に摂食できるよう十分な大きさでなければならず、清潔で、腐ったり、かびたり、酸っぱくなって固まり、または、まずい餌がないようにするものとする。また、牛は常に飲水可能な状態であるものとする。
牛舎の床は適切に排水され、牛舎と移動通路と保定枠は牛が怪我をしないよう、滑りにくくする(摩擦がある)ものとする。
移動通路、保定枠と牛房は、牛が怪我をしないよう、とがった角や突起をなくするものとする。
通路と門は、牛の動きを妨害しないように設計し利用するものとする。滑りやすい床は避けるものとする。溝を付けたコンクリート、金属格子(とがっていないもの)、ゴム製のマットまたは深い砂を用いることで、滑ったり転倒したりする恐れを最小限に抑えることができる。滑ることを防ぐには、静かに取り扱うことが必須である。門や保定器を使用するときは、牛に苦痛を与える可能性があるため、過度な騒音は最小限に抑えるものとする。
油圧、空気圧式及び手動の保定器具は、扱う牛の大きさに合わせて適切に調整するものとする。油圧及び空気圧式保定器具は、怪我を防ぐための圧力制限装置が設置されているものとする。動作部品の定期的な清掃と手入れは、適切な機能を確保するために不可欠であり、牛の安全につながる。
牛舎にある機械、電気設備は、牛にとって安全なものを使用するものとする。
ディッピングバス(浸漬槽)は、外部寄生虫制御のために肉牛の生産に使用されることがある。これらが使用される場合には、混雑の危険性を最小限に抑え、怪我と溺死を防ぐように設計、運用されるものとする。
農場での牛の積み込みについては第7.2、7.3、7.4 章に従って実施されるものとする。
福祉の状態を測り得る所見:取扱いに対する反応、罹患率、死亡率、行動、体重及び身体の状態の変化、外貌、跛行。
j)安楽死
病気や怪我をした牛は、治療を継続するか安楽死を行うか決定するため、迅速に診断するものとする。
安楽死の決定と実施は能力のある者が行うものとする。
安楽死の理由としては次のようなものが含まれる。
i) 重度の衰弱、歩行不能または起立不能になる恐れがある弱い牛。
ii) 起立しなかったり、摂飲食を拒否したり、治療に反応しない歩行不能の牛。
iii) 治療がうまくいかず、容体が急速に悪化した牛。
iv) 衰弱を引き起こす強い痛み。
v) 複雑骨折。
vi) 脊髄損傷。
vii) 中枢神経系の疾患。
viii) 慢性的な体重減少を伴う複数の関節の感染。
安楽死法については第7.6.5 条を参照。