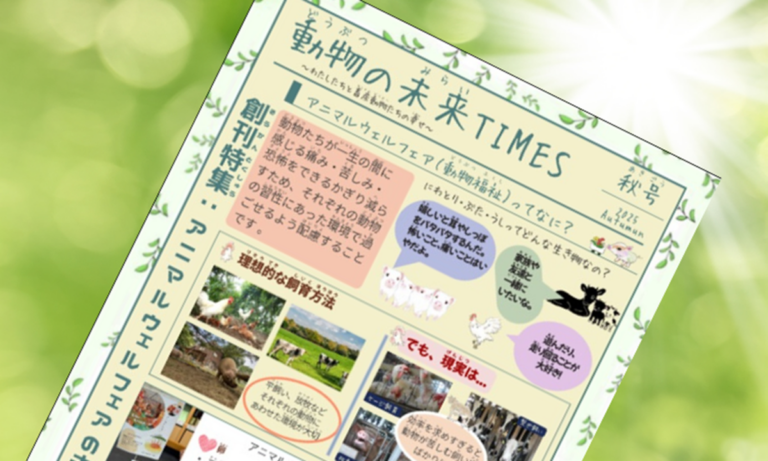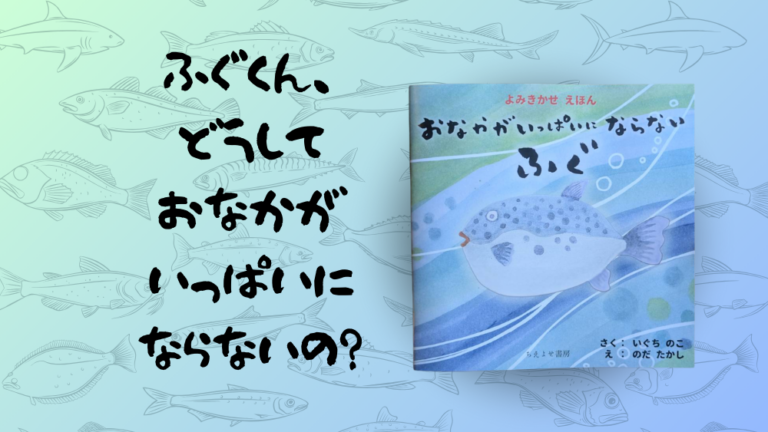ひよこの雌雄鑑別技術を教える養成所で、講習生一人当たり2万羽(履修期間は5ヶ月)を犠牲にし、ひよこのひどい扱いや、倫理観の欠如した感覚が明らかになった件で、養成所を運営する母体である公益社団法人畜産技術協会に改善のお願いをしていましたが、畜産技術協会からいただいた回答で、改善に向けて一歩進み始めることがわかりました。ただ、元講習生の話と食い違う点や、改善が不十分と思われる点があり、再度改善を求めています。
とはいえ、”アニマルウェルフェアの普及に取り組む団体”として真摯に向き合ってくれていることに感謝します。
畜産技術協会からの回答
最初にご要望並びにご質問全体に対するご回答をさせて頂きます。
アニマルウェルフェアの普及に取り組む団体として、弊会の実施する初生雛鑑別師の養成に対して、ご指摘を頂いたことに感謝し、真摯に対応をしたいと考えています。
初生雛鑑別については、卵内鑑別の技術が年々向上する一方で、我が国での技術活用の速度等が不透明であり、この間の卵や鶏肉の安定的な生産に不可欠な技術として、アニマルウェルフェアに配慮しながら維持をしていく必要があると考えております。
1:問題点の改善について
情報提供により、養成所には以下の問題点があると認識しています。
下記A~Lの問題点の中で、すでに改善されているものがあればその改善の内容を教えて下さい。
改善がなされていない場合、改善の計画及び改善を完了する時期を教えて下さい。
改善を行わない場合、その理由を教えて下さい。
不適切な環境
A.講習は夏で暑いにも関わらず適切な空調がなされていなかったA
初生雛鑑別師養成所では、講習生や職員、ヒナへの負担を減らすため用の業務用エアコン(2台)や扇風機等を導入しております。孵化後0〜3日の雛の適温は、30〜35度程度と言われており、現状では初生雛に対する夏の暑さの問題は大きくないと考えています。むしろ、湿度に対する配慮が必要と考えており、養成所では、到着時に雛箱に入っている初生雛の羽数を減らし(120羽→80羽)、更に換気のために扇風機を使い、風も初生雛に直接当たらないよう配慮し間接的に風を流すなど、初生雛の管理に必要な対応をしています。
法令違反の可能性もある虐待的行為
B.初生雛が絶食絶水で箱の中に入れられている
(回答)
初生雛の体内に残る卵黄中の栄養が消費されるまでに孵化後2〜3日を要するため、給餌の必要性は低いと考えています。また、給水についても、卵黄から一定量が供給されるため、これまでは無給水での管理をしてきました。しかし、近年の夏の高温期における初生雛の水分補給については、改善する必要性があると考えておりますので、飲水させる方法について検討する予定です。
C.箱の中には死んだ初生雛が一緒に入れられている
(回答)
初生雛の輸送に際しては、雛への暑熱等の影響を極力さけるため、風通しと換気のための空気動線の確保等に配慮し、施設到着後は、箱内の羽数の調整、温度か、箱の組み方を工夫しながら扇風機の風量や方向の調整を丁寧に取り扱っています。
その上で、死亡した初生雛がいた場合には、発見し次第、取り除いています。
D.箱の中には弱ってボロボロの状態の初生雛も一緒に入れられており治療または適切な安楽殺がなされていない
(回答)
講習生は、初生雛鑑別師養成所に入所後、最初の1か月程度は負担をかけないように優しく保定する練習から実習を開始し、次に初生雛負担をかけずに肛門を開くために脱糞をさせる技術の実習を行います。この初期の実習で初生雛を優しく扱うための基礎技術を習得し、その後、徐々に初生雛の肛門を開いて雄と雌を鑑別する技術の実習に移っていきます。養成所では、上記のように初生雛へのダメージを避けるため、初期の初生雛を保定する方法等の基礎技術の習得に時間をかけています。しかし、初期段階での失敗を完全に防ぐことは困難であり、基礎技術の習得が不十分な場合には残念ながら初生離にダメージを与えてしまうこともあります。また、発育不良や奇形等が原因で、元気のない初生雛が混じっている場合もあります。
箱の中で弱ったり、深刻なダメージを受けた初生雛を発見した場合には、初期段階ではその都度ベテランの鑑別師が安楽死処置を講じています。
E.指の力を入れすぎや複数回練習に使うこと等により、肛門からお腹の下あたりまで腹が裂けることがある
(回答)
初期段階で基礎技術の習得が不十分段階では、一部の講習生の中には肛門を開く際に指に力が入り過ぎ、初生雛にご指摘のようなダメージを与えることがごく稀ですが起こります。このため、ベテラン講師が徹底して、このような事故を繰り返さないように、爪の管理方法から細かく指導を行っています。なお、講習生が初生雛に深刻なダメージを与えた場合には、その都度、ベテランの鑑別師が安楽死処置を講じています。このような事故は初生雛が奇形等の場合に発生しやすいと言われているため、事故の発生件数を減らすために、事故を起こしやすい奇形と判断した初生雛については、今後は実習には使用せず安楽死処置を講じることとします。
F.Eについて、腹の裂けた初生雛に対して治療がなされていない
(回答)
残念ながら初生雛の腹が裂けた場合の治療は困難ですので、その都度、ベテラン鑑別師が安楽死処置を講じています。
G.解剖のための殺処分方法が首を叩きつける非人道的と考えられる方法である
(回答)
解剖に用いる雛については、現在、頸椎脱臼及び炭酸ガスによる安楽死処置を用いているところです。農林水産省畜産局の「家畜の農場内における安楽死に関する技術的な指針」付録IのWOARコード「第7.6章疾病の管理を目的とした動物の殺処分」に記載されている「二酸化炭素」、「頸椎脱臼」の手法を用いて安楽死処置しています。また、安楽死処置の方法については、同指針第6安楽死の手順1法令に準拠した安楽死の方法の実施【実施が推奨される事項】に、「安楽死の方法は、①頭部への物理的な打撃による方法(略)により即座に意識喪失の状態にした後、頸椎(略)を行い死に至らしめる方法」が掲載されているように、できる限り速やかに対象動物に苦痛を与えない方法として、頭部打撃とこれに続くついても安楽死処置の方法として用いる場合もあります。
H.上記殺処分を行った際に首がもげることがある
(回答)
少なくとも昨年はそのようなことは起こらなかったと聞いておりますが、基礎技術の習得が不十分な場合には、雛の頭を机の角で打撃及び頸推脱りが、力の入れ過ぎでご指摘のような結果となる可能性もあると思います。
なお、ご指摘を踏まえ、安楽死処置を行う講習生や鑑別師の心理的負担という点にも配慮する必要があると考えておりますので、熟練者による安楽死処置についてはより良い方法について検討して参ります。
I.給餌給水の徹底と弱った初生雛の即座の治療と淘汰は最低限行われるべきであるが、毎週1回殺処分が行われ廃棄に出されるが、B~Fのような状態で長期苦しむことになる
(回答)
弱った初生雛については、その都度、安楽死処置を講じています。また、実習に使用した初生雛については、毎週1回の安楽死処置ではなく、卵黄の栄養に果りがあるため、実習が終わったら直ぐに安楽死処置を講じています。
アニマルライツセンター様のホームページに掲載されたビニール袋内の初生雛の映像を確認致しました。炭酸ガスによる安楽死処置では、無意識状態になるまで一定の時間を要します。また、炭酸ガスの投入量が不十分だった可能性も考えられるため、安楽死処置が適切に実施されるように関係者に改めて指導を徹底します。
不要な苦痛
J.不要な解剖が行われている(解剖をして雌雄を判別する必要はない)
(回答)
肛門鑑別技術は、肛門の生殖突起の形状等から、初生雛の雌雄を判別する技術で極めて難しい高度な熟練技術とも言われています。
肛門の生殖突起は様々な形状のものがあり、一部の初生雛では生殖突起による雌雄の判別が極めて難しい場合があります。このような初生雛を鑑別した場合には、今後の肛門鑑別を正確に行うため、技術の定着化に資する手段として、安楽死処置を講じた後に、解剖により体内の生殖器の構造の違いを目視し、雌雄を最終確認(雌の場合には、左右の生殖腺の左側のみが卵巣として発達)する技術指導を、講習の最終段階において行っています。
講師の適正の不足、及び倫理面の教育不足
K.複数の講師が笑いながら初生雛を殺処分している
(回答)
畜産技術協会では、講習生のほか講師に対しても、アニマルウェルフェアの講習を毎年実施しており、皆、アニマルウェルフェアの重要性は十分に認識しています。また、初生雛鑑別師養成所の講師も講習生に対して、しっかりと指導を行っています。ご指摘のような事実が過去にあったとすれば、大変遺憾なことですので、改めて講師に対するアニマルウェルフェアに係る教育訓練を徹底してまいります。
L/初生雛の首がもげるなどしている状態を笑いながら作業する講習性がおり注意されない
(回答)
ご指摘のような事実が過去にあったとすれば、大変遺憾なことですので、改めて講習生並びに講師に対するアニマルウェルフェアに係る指導、教育訓練を一層徹底して参ります。
2:実習に利用される羽数について
一人の講習生が、卒業までの5ヶ月間で約2万羽の初生雛を実習に使用し、毎週殺処分をしていると聞いています。献体が必要であることは理解しますが、この羽数は過剰であり、代替方法も考えうるものです。
例えば死体を利用する方法により、生きた状態で慣れない鑑別をされ腹が裂けるなどの苦痛をなくすことができるのではないでしょうか。
精巧な模型を利用するなども、医学や獣医学での実習の動物実験代替法としてすでに利用されています。同様の方法を使うことで数を大幅に減らすことが可能です。
学校内での実習ではなく、孵化場での研修に変えることも選択肢の一つであるのではないでしょうか。
生きた動物での練習ありきで考えず、犠牲数の大幅な削減を検討してください。
(回答)
初生雛鑑別師養成所では、我が国の養鶏産業で不可欠な優秀な初生雛鑑別師を養成するために講習を行っています。このためには、一定数の初生雛を使用した実習により技術を習得せざるを得ません。しかしながら、ご指摘のように我が国のアニマルウェルフェアを普及推進する団体として、大学等の専門家の方々の力も頂きながら、できるだけ科学的かつ合理的に技術習得ができるよう検討をして参ります。
弊会と致しましても、アニマルウェルフェアの観点から講習に使用する初生雛の削減については、技術習得のレベルを維持しながら取り組んで行く必要があると考えており、技術習得の初期段階での模型等の活用を含め一部代替法の採用等についても検討したいと考えています。
また、現在も講習生の実習先等として孵化場様には、多大なご協力を頂いているところですが、鑑別師の育成に関する連携につきましても、引き続き関との調整を行っていきたいと考えております。
3:卵内雌雄鑑別法の積極的な推進について
科研費からは「孵化直後の採卵鶏雄雛の70億羽殺処分という人類が抱える大きな未解決課題の解決」のための研究に対して補助金が出されており、オスひよこの生後1日目の淘汰はその他の場でも度々課題として検討されたり、報道されるようになっています。これらの解決のためには卵内雌雄鑑別機材の導入と実用化が急がれます。
採卵鶏の孵化場では将来的に卵内雌雄鑑別法の導入を望む声があると業界団体より伺っています。
アニマルウェルフェアの流れは様々な社会課題の解決や食品企業の企業価値につながるものであり、否定することはできないものと思います。すでに貴団体でもアニマルウェルフェアを推進する事業をされております。
初生雛鑑別の養成所や資格を運営してきた貴団体はこの課題の直接的な利害関係者です。だからこそ、貴団体が卵内雌雄鑑別法を積極的に採用したいとする姿勢が、国や業界を動かす一つの原動力になります。実際には躊躇する原因を取り除くことに繋がります。
卵内雌雄鑑別法の導入や実用化を支援する取り組みを、早期に行い、公表してください。
(回答)
卵内鑑別技術が、採卵鶏の雄雛の殺処分の削減等からアニマルウェルフェアに即した技術であること、EUにおいては技術開発が進み、一部については現場での活用が始まっていることも承知しております。このため、講習生に対しても、EUの卵内鑑別の状況について、情報提供を行っています。
一方で、依然として開発途中の技術でもあり、機器のコスト、精度、処理スピード面での問題等もあることから、当該技術が我が国においても普及や開発されるまでの間は、初生雛鑑別技術も必要不可欠な技術と考えております。
弊会と致しましては、今後も更にアニマルウェルフェアに配慮した技術の改善や、社会の要請に適応しうる鑑別師の育成を行って参りたいと考えております。
アニマルウェルフェアを普及推進する団体として、大変、貴重なご意見を賜りましたことに、感謝申し上げます。
アニマルライツセンターからの再要望
この度は、初生雛鑑別養成所の課題について、真摯に向き合ってくださり誠にありがとうございます。
改善に向けた取り組みが見え、大変嬉しく感じております。
下記7点について、再度ご検討いただきたく、ご連絡いたしました。
1:温度管理について
湿度の改善をしてくださるとのこと、ありがとうございます。また、空調も行っているとのことでした。
しかし、元講習生によると、初生雛たちは「口を何回も開けて苦しそうに息が荒くなっていた」と述べており、これは高温によるパンティングである可能性も考えられます。
温度管理、密度、雛を入れたコンテナの管理状態を再度見直していただきたくお願いいたします。
2:雛の保管時の配慮
「風通しと換気のための空気動線の確保等に配慮」とのご回答でしたが、コンテナに入れ高く積み上げられ一列に置かれている状態が配慮されている状態でしょうか。
右の写真は火曜午前の鑑別講習に使用した後の雛ですが、積み上げられている状態で、最下部の雛、中段の雛、最上部の雛では環境が異なることがわかります。また温度も最下部と最上部では違いがあると思われます。
さらに、密度について「120羽から80羽」に改善しているとのことですが、80羽が適正とは思えません。
右の写真は火曜日の午前の鑑別講習に使用した後の雛ですが、これを適正というのは無理があります。(実際の羽数不明ですが写真からは50羽程度に見えます)
搬入後、実習後、両方の飼養状態をご確認いただき、再度改善をご検討くださいますようお願いします。
3:給餌について
給水については方法をご検討くださるとのこと、ありがとうございます。
一方、給餌については「初生雛の体内に残る卵黄中の栄養が消費されるまでに孵化後2〜3日を要するため、給餌の必要性は低い」とのご見解ですが、アニマルウェルフェア上は孵化後すぐに給餌することが望ましいことがわかっています。
孵化直後の給餌は免疫系の発達を促進し、ストレス耐性を向上させ、逆に、給餌の遅れは、ストレスホルモンの増加と感染症への感受性を高め、死亡リスクを増加させる可能性があります。
孵化直後の餌供給が腸の発達を促進し、ストレスホルモンの分泌を抑制し、雛の長期的な健康に寄与する可能性があると指摘されています。
孵化直後の給餌の遅れは、ストレスホルモンの増加や体重の減少を引き起こし、雛の生存率を低下させる可能性があります。
特に、48時間以上の遅れは致命的な影響を及ぼし、鶏のウェルフェアを著しく損なうと結論付けています。
このような背景から、ブロイラー養鶏ではオンファームハッチングと呼ばれる農場内孵化が増えてきていますし、私たちも生産者にはこの技術の導入の検討を要望をしているところです。
給水はもちろんのこと、給餌についてもご検討くださいますようお願いいたします。
4:殺処分のタイミング
「毎週1回の安楽死処置ではなく、卵黄の栄養に果りがあるため、実習が終わったら直ぐに安楽死処置を講じています」とご回答頂きましたが、再度、事実確認と改善をお願いします。
元講習生によると、月曜に搬入された初生雛は、実習に使用された後すぐには安楽殺されず、水曜日にまとめて安楽殺をされていたと証言しています。
もしかしたら貴団体のマニュアルではそのように規定しているのかもしれませんが、規定や規則がどうであれ、現場では守られないことは多々あります。効率化や、怠慢な勤務といったことは、よくあることですが、動物の命を扱う上ではあってはならないことです。
実習終了後すぐに、別部屋にて、安楽殺を確実に行ってください。
5:安楽殺方法について
改善を図ってくださるとのこと、ありがとうございます。
ただ、ご回答いただいた改善内容では不十分であり、再度要望させていただきます。
告発した講習生は、「青いバケツの中に袋を入れ、その中に初生ひなを次々と入れて講師に渡します。講師がそのバケツの中に二酸化炭素ガスを注入し、袋の口をしばる」という方法であったといいます。つまり、多数の雛が折り重なった状態の袋にガスを注入しており、これでは早期の致死は不可能です。
さらに、複数の動物の殺処分において、人の手で都度、二酸化炭素ガスを注入するというあいまいな方法は、雛の配置場所と属人的な要素と動物の個体の状態により結果にブレが生じることが容易に予測され、結果があまりに不安定であり、取るべき方法ではありません。
そもそも「家畜の農場内における安楽死に関する技術的な指針」にも書かれている通り、「脳幹反射のない(瞳孔の拡大や呼吸の欠如等)確実な死に至るまで、家畜を常に観察する」ことは必須ですが、袋に複数羽入れられた状態で死亡確認を確実に行うことは困難です。
つまり、複数羽を袋に入れて人間が二酸化炭素ガスを注入する方法は、安楽に動物を殺処分することも、指針に沿うことも難しいと考えられます。
一般社団法人日本種鶏孵卵協会では昨年3月に「ふ化場におけるアニマルウェルフェア推進ガイドライン~雛の安楽殺に関する推奨手法について~」を作成しています。より多くの羽数を殺処分する孵化場での改善が進む中、頸椎脱臼や二酸化炭素充填による方法では不十分です。
最低限、アニマルウェルフェアに対応するためには、アニマルウェルフェアの評価が済んでいる海外のガス安楽殺装置を導入することが必要と考えます。サイズ的にはキャビネット式ガス安楽殺装置などが考えられます。自家製の安楽殺装置もあるようですが、これはアニマルウェルフェア上の懸念が残っており、避けるべきです。
さらに、畜産業ではなく学ぶ場であることから、畜産業より安楽な殺処分方法が求められます。
二酸化炭素のみの殺処分は適切な装置を使えば”まし”ではあれど、苦痛を伴います。養成所では、イソフルランのような吸入麻酔薬を使った安楽殺を採用してくださるよう、切にお願いします。
これについては、国内では野生動物の安楽殺で実用化(イソフルラン混合の吸入麻酔で意識喪失後、CO2暴露による致死)しています。ある大学医学部の実験動物(ひよこ)の殺処分方法としてはイソフルランと空気混合気体を、装置を用いて吸引後、より確実に致死させるため頸動脈切断による脱血させる方法での安楽殺が規定されています。
6:雛の扱い改善のためのカメラの導入
「都度ベテランの鑑別師が安楽死処置を講じています。」とのご回答がございますが、過去の講習生によると「お腹が裂けてしまい腸が出ている状態で歩いている初生ひなが放置されていた」とのことでした。
これは畜産の現場でもあることですが、マニュアルなどで注意書きがあったとしても、現場では守られないといったことが多々あります。これは多数の生きた動物を扱うからこそ起きることであり、いいかげんになったり、見逃したりといったことが起きがちです。数が多く、なおかつ雛や鶏のように小さな動物の場合、1羽1羽が尊い命であることを忘れがちになることは、人間の心理としては容易に起こりうることです。そのことを考慮した指導および監督をする必要があります。
と畜場では現在、アニマルウェルフェアや品質の管理のために監視カメラを導入することが国内でも始まっています。カメラが回っていることだけでも、虐待や雑な扱いの予防になりますし、事故があったときの検証も可能になります。
講習生および講師が雛を扱う場において、監視カメラを導入してくださいますようお願いします。とくに雛は小さいため、高いところからの監視だけでなく、雛の保管場所や安楽殺を行う場所、弱った雛を入れる箱など個別に設置してください。
また、そのデータは講師ではなく、離れた場所にいる貴団体の担当者が随時見れるようなネットワークを作り、虐待の防止に努めてください。(通常売られている監視カメラもオンラインで見れますので容易であると思います)
また、貴団体には獣医師が勤務されているものと思います。獣医師が養成所にきちんと関与し、適切な扱いを監視指導してくださることを期待します。
7:不適切行為があった場合のペナルティ
虐待や講師として不適切な行為(笑いながら殺すなど)が発生した場合の、行為者へのペナルティを明確にしてください。
例えば海外では、虐待が判明した場合即刻解雇などの規定を持つ食肉企業もあります。
お忙しい中大変恐縮ですが、以上につきまして、2025年2月末日までに下記連絡先までご回答をいただけますよう、お願いいたします。