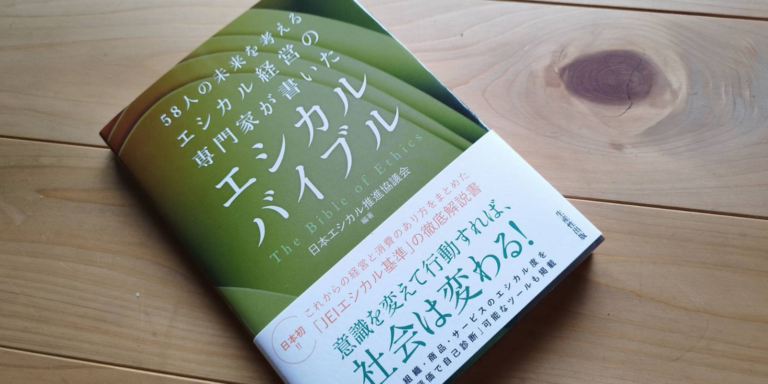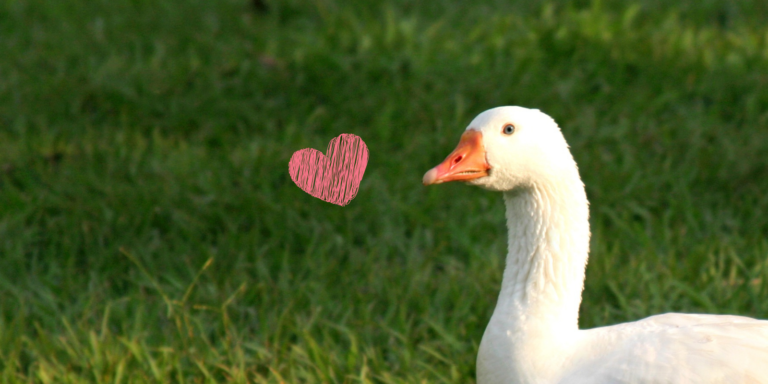アニマルライツセンターも参加する多分野の34の団体が集まる「消費から持続可能な社会を作る市民ネットワーク」(SSRC)では、2017年3月28日に『企業のエシカル通信簿』を発表しました。
この『企業のエシカル通信簿』は、「消費から持続可能な社会をつくる市民ネットワーク」が、各参加団体の専門性を生かして持続可能な社会・環境・消費者・人権・社会・平和・アニマルウェルフェアの7つの大項目、約50ページから成る調査票を作成し、公開情報をもとに調査して企業のエシカル度を調査したもの。初年度は、加工食品とアパレル(衣料品)の2業界の売り上げ上位各5社、計10社を対象に調査した後、各企業に調査結果を送付し内容の確認を求め、その回答も考慮した上で最終的なレイティングと評価が行われました。
幅広い分野にわたり、市民目線で企業を評価する取り組みは、日本初のものです。

レイティング結果
| SD | 環境 | 消費者 | 人権 | 社会 | 平和 | 動物 | |
| 明治H | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 |
| 日本ハム | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 味の素 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 1 | 1 |
| 山崎製パン | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| マルハニチロ | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| SD | 環境 | 消費者 | 人権 | 社会 | 平和 | 動物 | |
| ファーストリテイリング | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 |
| しまむら | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| ワールド | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| オンワード H | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 青山商事 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
動物の評価
※それ以外の項目の評価もとても興味深く、またとても勉強になるものです。「消費から持続可能な社会を作る市民ネットワーク」からすべての結果がご覧いただけます。
動物飼育に関わる点において、企業の取組みの姿勢、管理の方針、具体的な改善の進捗、その他環境や人の健康への影響についてを、国際的な調査を参考にしながら、一部日本向けに改変し、設計されました。
結果のみを見るのではなく、動物への配慮についての取り組みの姿勢や過程、部分的な取り組みも評価できるように設計されている。
ご注意いただきたいのは、この項目では各企業の事業内における動物への配慮を評価しており、事業外での動物保護に関わる社会貢献活動等は範囲外としています。
A:アニマルウェルフェアの基本的、包括的なポリシー、方針等
については、企業として取り組む方針を立てているのか、また意識した商品があるのかを評価しています。
ファーストリテイリング、明治ホールディングスにおいて、取り組みが見られました。
B:ガバナンスと管理
アニマルウェルフェアをどのように達成し、評価していくのかという手順については、どの企業にも取り組みは見られませんでした。
C:アニマルウェルフェア 具体的な取り組み
具体的に改善するべき動物の扱いへの取り組み状況を調査しました。
毛皮や残酷な手法を経たウールやダウンを扱わないとしているファーストリテイリングや動物実験を避ける方針を持つマルハニチロや味の素を評価しています。
D:環境・人権への影響
動物製品を作る過程で影響の出る環境汚染や国産飼料を使うかどうかなどの社会的課題について調査しました。
マルハニチロはMSC認証を取得する企業と提携するなど行われ始めていますが、じっさいに漁獲量が制限されるなどの自社事業への影響が出てきたことに対処するため、取り組みが行われていました。
毛皮や革などの加工過程で使われる薬剤による環境汚染及び生産地の健康被害が明らかになっているところであるが、㈱ファーストリテイリングでは皮革に限らず「危険化学物質の排出撲滅に向けた取組み」を掲げており、NGO等の意見を取り入れながら有害化学物質の排出削減・撲滅に向けた取り組みを継続しそれを公開しており、評価できました。
総合評価
ご覧いただいている通りファーストリテイリングが3を獲得しており、これはこれまでの改善の経緯からみると、国際的なプレッシャーにより改善が進んできていると分析します。
それ以外の企業は残念ながら1でした。なかには何一つ取り組みが行われていなかった企業もあります。
動物の問題となると幅広く、利用形態も様々であること、人の問題のほうが先ではないかと考えられることがおおいこと、どのみち犠牲をゼロにはできないからということに、取り組みを躊躇するまたは取り組まなくてもよいのではないかと考える要因があると感じています。
企業のみなさん、動物に配慮するための一歩を
企業として取り組みはおもに2つの方針にわけられます。
1:飼育状態を改善すること
2:苦しむ動物の数を減らすこと
です。
1:飼育状態を改善すること
たとえば、慢性的に動物にストレスを与える、バタリーケージをエイビアリーシステムに切り替えることや、妊娠ストールでの拘束飼育を群れ飼育に切り替えること、痛みのある取扱、例えば麻酔無しでの去勢や尻尾や角の切除などは、すでに改善方法が確立されています。
また、日本独自の問題として、例えば、と畜場で22時間拘束されるにも関わらず水が与えられないということが、豚の85%、牛の50%のと畜場でおきていますので、こういった最低限の福祉を担保できているのかどうか、という点も評価されます。
2:苦しむ動物の数を減らすこと
もう一方で、毛皮やフォアグラ、化粧品や食品分野での動物実験のような、「これを使わなくてもよいであろう」と判断できるものに関しては、動物を利用しないという選択をとることが評価されます。
さらに、特に1の改善については一気に変換ができるものではいため、数年、若しくは十数年かけて移行することが示されていれば、私たちはその判断や姿勢を評価することができます。
取り組む意義は大きい、または大きくなる
動物の問題は後回しにされがちですが、一方で、動物の現状は想像以上に悲惨で市民の心を強く揺さぶります。
だからこそ冷静に考えられない人が多くなるという側面もありますが、知れば80%の市民が、企業は動物の状況を改善してほしいとこたえるのです。
その悲惨さを改善する方法がすでに欧米を中心にとられ、他の東アジアでもすすんできていることを考えると、対応しないリスクは大きいと考えられます。
非貿易的関心事項として動物福祉は重要になりつつあるなか、2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向け、日本企業への注目はあつまりますので、投資面でのリスクも大きくなる可能性もあります。
また、動物の問題に取り組むメリットはリスクに対処するという点だけでなく、生産者にとっては、動物福祉に配慮した環境で生きる動物と接することは精神的なケアになるという点があります。
密閉式のバタリーケージシステムの中にはゴーグルと防じんマスクをして入り、急いで出てきますが、放牧やエイビアリ-システムの養鶏場には何時間いても飽きないといいます。
畜産物の品質を流通等のみでだけでなく飼育、と畜からの品質向上がなされることは、消費者からの評価を得られることになりますし、商品の魅力のひとつになることでしょう。
消費者や社会へのよい影響もたくさんあります。
今回、動物の項目はあまり高くない評価でしたが、プロセスや取り組みの意志も評価するこの通信簿を向上させることはそれほど難しいものではありません。
来年、再来年と、企業の公開情報の中に動物福祉や愛護、またはその他平和や人権等についてのより多くの情報を見つけることを楽しみにしています。