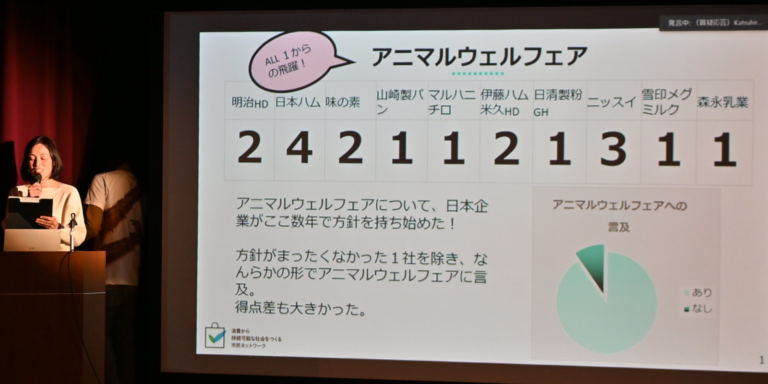東京理科大学 生命科学研究所と薬学部での動物実験施設のずさんな管理と動物の福祉を無視した動物の扱いが、内部告発によって明らかになった。その告発により、東京理科大学生命科学研究所および薬学部の教授陣(及びその門下にある学生)の実験動物に対する倫理観の欠如、非常識さが露呈した。
内部告発の内容
2004年4月、Stop Animal Test! Campaignに、東京理科大学生命科学研究所及び薬学部の動物実験施設で起こっている問題について告発があった。
告発のあった施設
・東京理科大学 生命科学研究所
・東京理科大学 薬学部
問題点
- 遺伝子改変動物の管理を怠っていた。今は何の変化もないかも知れないが将来、環境、生態系、ゆくゆくは人体への影響も考えられる。
- 常識を超えた過密飼育、断尾、断頭、断手、共食い、餓死など、虐待的行為が日常的に起こっていた。
- 繁殖記録を怠り、マウス、ラットの系統の把握は不可能な状態であった。繁殖記録は正確なデータをとるには必ず必要なはずである。
- 何らかの外科手術(脳に電極を埋めるなど)が行われた後の術後のケア、配慮が行われていなかった。
- 大学という教育の場では、上記のような動物への扱い・倫理観も学生に受け継がれていく。このことが学生と動物の将来に与えるマイナス面は計り知れないほど大きい。
現在、大学内部での調査を行っている(行った)ということだが、大学自身での調査であり、その真偽を確かめることはできない。文部科学省は立ち入り検査までする根拠は今のところ無いと答弁しているが、過去に遺伝子組換えマウスを施設外で飼育していたことを認めているうえ、市民が野田市保健所に逃亡しているマウスを発見して通報までしている。これで立ち入り検査を行うことができない場合、一体どのような状況で立ち入り検査が行われるのだろうか。
動物の管理
外部と遮断した実験施設で行わなければならない遺伝子改変マウス(特定の遺伝子を破壊されたマウス)を、一般の研究室に持ち出し実験を行っていた。
東京理科大学は、「外界に逃げることはなく、感染力もないため、人体や自然界に影響を与えることは考えられない。」と説明したが、施設周辺で実験動物と思われるマウスが逃げ出しているのを周辺住民が発見し、2003年10月に野田市保健所に通報した。この通報を受けて野田市保健所は大学を訪れ調査を行ったとしているが、施設内への立ち入り検査は行われず、施設の外を案内しただけでその実態をつかむにはいたらなかった。
また、東京理科大学は「マウスは免疫力が低いため自然界では長生きできない」としているが、その弱いはずのマウスを、専用施設の外で飼育し、長年実験に使用してきた。つまり、通常の雑菌のある場所でそのマウスたちは充分に生きることができるということではないだろうか。
遺伝子改変マウスが外界で繁殖することは大いに考えられ、現在はその変化、影響は表面に出なくても、将来、未知の問題が起こる可能性がある。
未知の問題とは、たとえば生物の多様性・生態系に影響が出ることや、異常な繁殖力を持つスーパーマウスの出現や、そのマウスが人間にとって危険なウイルスを媒介するようになるなどが考えられる。
さまざまな危険性をはらんでいるため、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」が昨年施行され、その厳重な管理が求められている。
動物虐待
動物福祉・倫理観の欠如した飼育を行っていた。その実態と、東京理科大学の研究者が持つ感覚は、常識からかけ離れた驚くべきものであった。
■5匹用のケージに37匹、10匹用のケージに47匹のマウスを入れる。(体が重なり合いケージは熱くなる状態)
規定数をオーバーした過密飼育は日常的であった。
■あまりに数が多すぎるため、大量の水と餌を与えても次の日にはなくなってしまい、その中で共食いがおきる。
■同じケージ内で繁殖を繰り返す。(何世代にも渡っているため、近親交配もありうる)
■ケージのふたをしめる時に尻尾や頭が引っかかり、不注意のためそのままふたを閉められて尻尾・頭が切断される。
■ケージのふたに手が引っかかりぶら下がったままになる。
など、多くの虐待が起こっていた。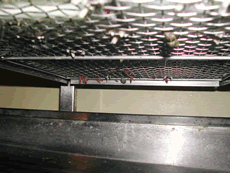
繁殖管理
通常、妊娠した動物は個別のケージに移され、子供が生まれれば子供の数も記録し、子供が離乳するまで母子は共に過ごす。しかし、この2施設では繁殖記録が取られないばかりか、1ケージ内で2匹のマウスが子供を産んでいたり(つまりその時点でケージ内には大人のマウス5匹とその子供たち約20匹が同居していることになる)、子供を産んだばかりのラットがすぐにこう配することになってしまったりしていた。
このようなずさんな繁殖で正確なデータを取ろうとすることは、あまりに乱暴な科学である。
写真1のケージの奥に、産まれたばかりの小さな赤いラットの赤ちゃんがいる。このケージの床は粗い網で、この小さなラットたちは普通に寝そべることができない。写真2はこのケージを下から映したもの。ラットの足の大部分が網からはみ出している。実際に脱落し、死亡してしまったこともあった。(網ケージの下は、フン等を効率的に掃除するため定期的に水が流れる仕組みになっている。告発者は何度か排水溝に流された死体を発見している。
 実験後の傷のケア
実験後の傷のケア
何らかの外科手術(脳に電極を埋めるなど)が行われた後の術後のケア、配慮が行われていなかった。動物福祉の観点からも、実験結果に与える影響からも、大きな問題がある。
写真のラットは、頭部への外科手術を受け、その後も長期にわたり(5ヶ月以上)実験が行われた。しかし、保温の配慮は一切行われず、網飼いのままであった。毛が逆立ち、耳や尾は貧血を呈している。
頭部の広範囲(ラットにとって)にわたる外傷のため、皮膚はなかなか再生されず、脳もむき出しのままである。毛に付着した赤いものが血であることは容易に想像がつく。
教育施設としての責任
この大学ようなずさんで非倫理的な管理を行う教師を持った学生は、やはり同様に動物福祉や正しい管理方法・倫理観を習得することができない。大学という教育の場では、この事例のような動物への扱い・倫理観も学生に受け継がれていく。このことが学生となにより動物の将来に与えるマイナス面は計り知れないほど大きい。
国会質問
これら問題の大きさに、参議院の谷博之議員が告発者の証言と野田市保健所等の情報に基づき、文教化学委員会と厚生労働委員会において、質問を行った。(この模様は参議院サイトで中継された)
議論の内容
| 5・11 文教化学委員会 |
|
(要約***敬語略) 谷議員;東京理科大学生命研究所では5年前から、同大学薬学部では昨年の野田市移転当時から、内規に反して、遺伝子改変動物を施設外の研究室などで飼育したり、容易に逃げやすいビニール袋に入れて運んだり、繁殖記録も行われていなかったりした。特に悪質な安部教授(元帝京大学副学長の薬害エイズ裁判で有名になった安部副学長の息子)(=当該動物実験施設の管理責任者)の研究室では、5匹のマウスしか入らないケージに、37匹ものマウスを入れていた。尾は切れ、(事故で)頭は飛び、最後には餌を与えないために共食いをするという実験動物の管理の仕方をしていた。なおかつ、この生命科学研究所の安部研究室では、97年ごろに、内規で禁止しているマラリア原虫の投与実験も強行したこともあった。 川村文科省大臣;理科大学側からは「現在は適切な管理を行っているが、過去において、必要以上に動物を繁殖させていた、あるいは飼育管理を請け負った会社から指摘されたような事実が一部あった」という報告があった。 谷議員:私は完全に改善されたとはまだ見ていない。今年の2月に遺伝子組み換え生物規正法(遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律*平成15年6月18日法律第97号)が施行された。この31条には、強制立ち入りができるという条文がある。大学側の回答を裏付けるという意味からも、直ちに立ち入り検査をするべきと思っている。 石川研究振興局長;東京理科大学に対し説明を求め、法令に基づいて適正な措置がとられているという報告を受けている。また、現在は法令違反の恐れがあると判断される事実は認められていないので、法律に基づく立ち入り検査を実施するまでの必要性は認識していない。 谷議員;内部からのいろいろな指摘があるのだから、指摘された事実は確認しなくてはいけない。 石川研究振興局長;業者からの様々な指摘について、東京理科大学から状況聴取している。現在、改めて大学で調査をするということで、学外の有識者を含めた特別調査委員会を設置をし、調査を行っているらしい。その調査の中で一層明らかにされると考えており、そういった事柄等も踏まえ、適切な対応をとっていきたい。 谷議員;ぜひこれは今後の動きを注目したいと思っている。 石川研究振興局長;各大学において動物愛護管理法、基準、学術審議会の報告等に基づき、指針や指針の適切な運用を図るための実験委員会等を設け、各大学においてそれぞれ自主的な管理を行っている。学術研究や学問の自由等の性格にもかんがみ、大学の自主性や或いはその自立性を尊重しながら実施をしていくことが適当だと考えており、法律に基づく立ち入り検査の導入等については、関係者の意見等も踏まえて慎重に対応する必要がある。 谷議員;管理委託業者が(実験動物の飼養を)やっていると思う。大学の研究施設で直接行うところもあるが、生き物だから当然責任ある管理者がいて管理しなくてはいけない。管理を専門で行う委託業者は、全国に5社ほどあるが、業者の数が足ないので、ビルメンテナンス会社などが副業で行っている。そうすると、動物の専門家ばかりではないため、適切な管理ができているか疑わしい例も出てくる。実験動物の管理には一定の資格や水準を持った業者があたるべきだと思う。最低でも届出制あるいは許可制のような形で業者を決めるという風な形に持っていくというのが最善の方策ではないかと思う。 石川研究振興局長;実験動物の飼養等作業を外部の業者に委託を実施する場合、充分な業務能力を有する業者の方に委託を行うことが基本であり、大切である。その上で、大学等の研究機関における自主的な管理の元で、適切な飼養管理が行われるべきという認識をしている。 谷議員;施設外飼育、過密飼育、繁殖記録のずさんな管理など、これでまともな研究や国際的評価ができるとは思えない。薬学部が6年制になれば、時間的余裕もできるので、普通は福祉というと人間の福祉ということに使われますけれども、動物にも福祉がある。生き物なんです。その実験動物をどうやって数を減らしていくか、いかに動物に苦痛を与えずその貴重な命を臨床のために使うかが基本。したがって動物実験代替法、あるいは生命倫理に関する教科、授業に力を入れる必要性を強く感じている。 副大臣;動物もこの世に生を受けた限り、やっぱりその生を全うすると、それが権利うんぬんということになるかどうかわかりませんけれども、当然なことだろうと思っている。先生から非常に大事なところをご指摘いただいた。こういう本当に隠れたしかし大事なことについても、思いをいたさなければならないろ思っている。薬学教育におきましては、平成14年8月に日本薬学学会におきまして、薬学教育モデルコアアリキュラムを作り上げたところであり、その中にも全ての薬学生が卒業までに身につけるべきことというタイトルで、動物実験における倫理について配慮をすることと、代表的な実験動物を丁寧に適切に取り扱うということをわざわざ書き上げている。医療人にとってたしかな倫理観を身に着けていくことは、当然基本的な事項と考えており、モデルコアカリキュラムを踏まえて、この問題に関する教育が充実されるよう、各大学を指導していきたいとこう思っている。 |
| 5・13 厚生労働委員会答弁 |
|
(谷議員の質問は前日とほぼ同内容のため、省略。)
坂口厚生労働大臣;昨年の10月、感染症法を改正し、動物を薬学調査のために対象として明記した。また、動物を媒介する4類の感染症について消毒薬等の動物の駆除等、対処を行えるようにした。動物と人間と共通の病原体や病気もあるので、動物を飼育して研究をする際、動物の管理が非常に大事になる。薬学部だけでなく、医学部や、他の研究所にも共通する問題だが、多くの病院は実験動物の管理に非常に気を使っているし、中には実験動物担当教授を作ったところもある。その遺伝的なものから、飼育の問題や感染症の問題から、非常に気を使っているところがある。実験の基礎になる問題だから、非常に大事であるし、周辺の住民の皆さん方の間との問題も存在する。行き届いた管理が行わなければならないことは間違いがない。我々も今後十分に注意していきたいと思っている。 遺伝子組み換え動物規制法に基づく立ち入り検査に関して
坂口厚生労働大臣;地域の保健所がそうした役割を担わなければならなず、対応できるようにしていかなければならない。 |
東京理科大へ要望書提出
飼育数について
①生命科学研究所の動物実験施設では、収容数を大幅に超えたマウスの飼養を行っていたとの情報がありますが、その真偽をお教えください。
②5匹用ケージに37匹のマウスが、10匹用ケージに50匹を超えるマウスが詰め込まれていたそうですが、その事実を東京理科大学としてはどう捉えているかお教えください。
③貴校では、これら過密飼育についての調査はおこないましたか。
④現時点において、過密飼育は改善され飼育数は規定に違反していませんか。
動物の状態について
①過密飼育に伴い、頭や尾がケージのふたに挟まり断頭・断尾するということがあったとのことですが、その真偽を把握されていますか。
②ケージのふたを閉めるときの不注意で、足が挟まったまま宙吊りになっていたということがあったとのことで すが、その真偽を把握されていますか。
③出産時に網のケージを使ったことによる陥落・マウスが挟まる等の事故があったとのことですが、その真偽を把握されていますか。
システムについて
①貴校には、動物実験の倫理規定を定めた指針および審査をする委員会はございますか。
ありましたら、ご回答と一緒にお送りいただけますようお願いいたします。
無い場合、今後作成する予定はございますか。
②貴校では、研究者および学生に対し、実験動物の福祉、倫理についての講義・講習はございますか。
現在行っていない場合、今後行う予定はございますか。
③研究所の自己管理による実験動物の福祉には限界があると考えられますが、問題のあった研究者や学生に対し、一時的調査だけでなく引き続き監視を行っていらっしゃいますか。
その他について
①この度の事件についての調査委員会の最終報告書を公表してください。
②安全管理体制の強化を図る、とのことですが、具体的にはどのような事を行いましたか。
今回内部告発によってこれら事実が明るみに出ましたが、今後、意見を抑制し事実を隠されるのではないかという懸念を私たちは抱いております。内部告発は、英語では「Whistle-Blowing(笛を吹く)」と言い、警鐘を鳴らすという意味を持ちます。今回の内部告発は貴校の研究と、ひいては実験動物の尊い命を無駄にしないための警鐘であったと考え、今後、施設およびシステムの改善をし、遺伝子改変動物の管理だけでなく、動物実験福祉にも取り組んでいただけますよう、お願いいたします。
また、東京理科大学は、理工学系研究では大変評価も高く、その名が全国に知れている大変有名が大学ですので、生命科学研究所と薬学部の実験動物のずさんな管理、生命の倫理と福祉を無視した飼育には多くの国民が落胆し、大きな不信感を抱いております。このたび明らかになった実態はそれだけ大きな問題であると思います。
最後に
動物実験の現場には、私たちの知らない同じような虐待があると想像されます。
それは、単に隠されて明らかになっていないだけに過ぎません。
動物実験が必要だと主張するのであれば、動物たちがどのように扱われ、どのように苦しみ、それを実験者がどのように捉えて実際に福祉に取り組んでいるのか、それを社会に公表してください。
社会に容認を求めるのであれば、公開することは当然のことです。
企業秘密にすべきは、その薬品の詳細などであり、秘密を守った上で動物実験自体は公表することは可能です。工夫の仕方はいくらでもあります。
さらには、その飼育現場、実験後の動物の状況などは、より容易に公開できるはずです。
企業秘密という隠れ蓑は、通用しません。