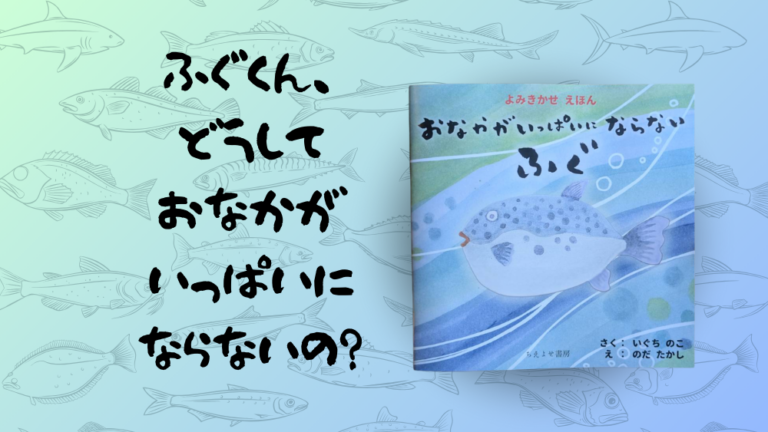日本女子大学家政学部 細川幸一教授
ペットを家族同然に思う人が増えている。コンパニオンアニマルという言葉もよく聞かれるようになっている。一方で、ペットに対する虐待や遺棄、ペット産業での粗雑な扱いなどがニュースとなることも多い。
他人の動物を殺したり傷つけたりした場合は刑法の器物損壊罪として処罰され得る。しかし、この規定は動物の所有者が同じことをしても適用されない。他人の物を壊した場合の罪であり、また動物は単に物としてしか扱われない。一方、動物愛護管理法の定める動物殺傷罪は所有者の行為に対しても適用され、器物損壊罪が1年以下の懲役又は100万円以下の罰金であるのに対して、愛護動物殺傷罪は5年以下の懲役又は500万円以下の罰金を規定しており、かなり重い。すなわち、動物愛護管理法は同法の定める種類の動物に限るが、動物は単なる物ではなく、「動物が命あるものであること」(同法の基本原則)に配慮しているからだ。
しかし、現在問題になっているのは民法の規定だ。日本の民法においては動物は権利の客体としての所有物にすぎない。しかしながら、欧州では近年、民法上、動物は単なる物ではない存在として認められ始めている。
例えば、ドイツでは1990年改正民法が、「動物は物ではない。動物は特別の法律によって保護される。動物については、別段の定めがない限り、物に関する規定を準用する」と規定した。
フランスでは2015年改正民法が、「動物は、感覚を備えた生命ある存在である。動物の保護に関する法律を留保して、動物は財産に関する制度に服する」との規定を置いた。
日本の法律上の課題
では日本の現行民法で何が問題となるのか?
民法上、動物は人間のように権利の帰属主体となることはできない。例えば、飼い主が自らの死後、ペットに対して財産を遺したいと考えたとしてもペット自身に財産を承継させることはできない。また、ペットが何らかの事故によって負傷あるいは死亡したとしても、あくまで物と同様の扱いを受けるので、人が負傷あるいは死亡した場合のような高額の慰謝料を請求することはできない。さらに、所有者の自宅等で虐待等があっても他人が動物を救済できない。あるいは自動車内に長時間動物が放置され、所有者の居所が分からないような場合に、動物愛護団体などが窓を壊して救済したとき、逆に法的な責任を問われる可能性がある。警察に通報しても、警察官は窓を壊すことをためらい、通報者が窓を壊すことを警察官が止めた。
権利主体としての法人
そうしたなかで、動物に法人格を与えて権利の主体として位置付ける考えが動物法学者だけでなく民法学者の間でも検討されている。日本の民法は権利主体として人間(自然人)だけではなく、法人を規定している。例として、株式会社や学校法人などだ。そこで、動物にも法人格をあたえてはどうかという指摘である。かなり唐突に感じるが、動物に法人格を与えることは、自然人と同じ権利を全て付与することではない。現在の人間社会を前提として、想定される動物の権利の内容は、不必要に殺されたり、虐待されない権利である。それによって動物保護の新たな可能性を探ろうとする試みだ。ただし、動物自身は権利を主張し、裁判を起こすことは当然できないから、動物になりかわって動物愛護団体などが権利を行使することとなろう。
民法学者の河上正二東大名誉教授は著書のなかで以下のように述べている。
「少なくとも生命・感覚を持つ存在としての動物に一定の法的配慮をすることは、人間の尊厳の制度的基礎となってきた人・物の峻別と相いれない発想ではない」。
実現への壁や検討課題は多いが、まずは国会あるいは法務省の法制審議会で真剣に議論してみてはどうか。