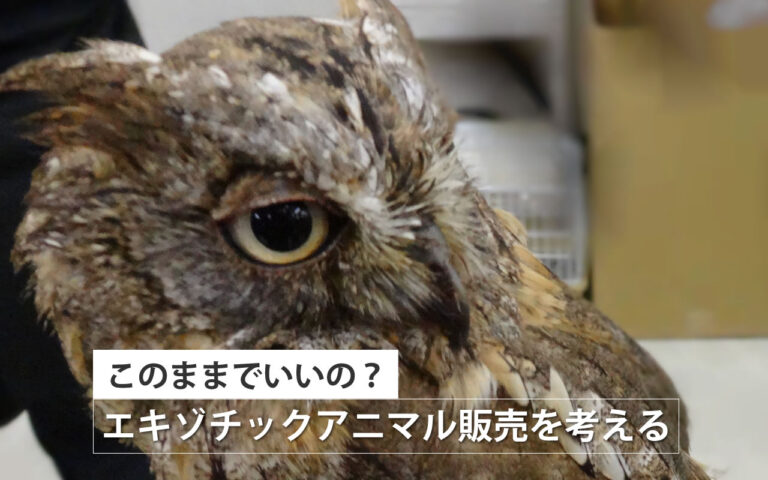「いのくら」保健医療部会
神奈川県保健福祉部との交渉 2013
ARCは、「いのくら(県民のいのちとくらしを守る共同行動委員会)」の保健医療部階の位置団体として、毎年神奈川県保健福祉部交渉に出席し、以下の点について要求し、交渉しました。その内の論点のあるものについてご報告します。
1.殺処分数の減少や動物の適正飼育について
■ARC : 県から不妊・去勢手術の誓約をして犬猫の譲渡を受けた方が、動物保護センターに対して、の手術報告をする「連絡表」の回収率を示すこと。
■県 : 譲渡の別 回収率(%)
犬 保護センターからの譲渡 88%(2011年度)
ボランティア・個人経由 70% ただし事後の報告で95%を確認
猫*2 保護センターからの譲渡 60%
ボランティア・個人経由 64%
*2 猫については、連絡票の報告を受けていない飼養者に対し、不妊手術を実施しない理由(死亡、高齢等)をすべて確認している。
今後も、連絡票の回収率の向上に努める。
不妊去勢を行ったかどうかの連絡表の改修については、未回収の場合は追跡調査を行うようになっており、進展が見られました。しかし、連絡が取れないケースが1件あったとのことで、譲渡の際の適正な飼育者かどうかの判断には注意する必要があります。さらに、譲渡して①年以内の死亡の原因は不明です。
2.引取りを行わなかった場合の対応について
■ARC : 殺処分数は、単に引取りを断ることではなく、不妊去勢手術の完全履行と終生適正飼育によって減少されるべきものである。しかし、自治体の多くは処分数(引取り数)の削減目標を追うあまりに、引取りを拒否する傾向がみられる。拒否された後で、狭いケージに閉じ込める・散歩をさせない・不衛生な状態で放置する・エサを適正に与えない・しつけを放棄するといった「飼い殺し」状態に置いたり、無責任譲渡または遺棄される動物が発生することが懸念される。
引取を行わなかった場合、その後、動物が適正に使用されているか確認すること。
■県 :動物の引取りを申し出る者に対する指導の結果、飼養者が再考を検討することとなった場合、その者の住所、氏名等を行政が把握していない(現状する予定はない)ため、追跡調査は困難である。
なお、引取りを行わず、再考を促した飼養者が飼養を継続する場合には、適正に飼養するよう指導する。また、再考を指導した場合には、当該飼養者に対し、引き続き、当該動物の適正飼養を指導するとともに、再考した結果、飼養継続が困難であると飼養者が判断した場合には、再度、相談するよう指導している。
保健所に連れて来られる動物は、それまでも不幸で不適切な飼育下にあったことが多いのです。適切な環境を提供できないなら、動物を穏やかに死なせる行為は、より福祉的であるというのが、世界的なスタンダードです。引取を行わなかった場合において、その動物の飼育環境を確認しないということは、動物にさらなる苦しみを味あわせる可能性が高いのではないでしょうか。全件が難しくても、無作為に確認しに行くことを示唆するだけでも、違うはずなのです。