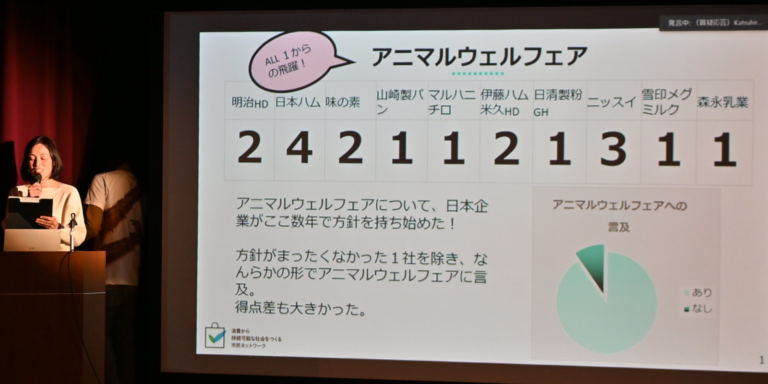「我々としては法規制で強化される、気分的にはやはり(研究が)やりにくくなる、ということで悪影響ということになると思います・・・」
ちょっとまって、そんな理由だったの?!
この驚愕の発言が飛び出したのは、2018年3月15日(金)に超党派の「犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟」の動物愛護法改正第16回プロジェクトチームの会議の場。

議論がほとんどされてこなかった実験動物についてヒアリングと議論がされた。
日本実験動物医学会の下田耕治理事(慶応義塾大学医学部教授 動物実験センター長)と久和茂理事(東京大学大学院農学生命科学研究科 獣医学専攻実験動物学研究室 教授)が、また国内の動物実験の状況について出版したジャーナリストであり時事通信社の森映子記者から、ヒアリングがされた。日本実験動物医学会とは「日本獣医学会の分科会として、実験動物の健康・医学ならびに福祉に関する研究、教育の推進、及びその普及を目的として活動」をしている団体であり、まさに動物実験の利害関係者だ。
日本実験動物医学会は、改正を行う理由はまったくないと主張し、森記者は登録性を含め改正をすべきだと主張した。
冒頭の驚きの発言は質疑応答の中で出た。質疑応答の中のいくつかを取り上げる。
外部検証というけど、それは内部検証
四十一条しかないのであるから日本の遅れているのではないかという指摘がなされた。
下田氏は、
各国には動物愛護と科学上の利用が別れているものがけっこうある、それを我が国では【2006年体制】では動物愛護法のもと告示に則って我々は動物実験を適正にやるという方針でやっている。
我々のシステムはアメリカ、かならのシステムを参考にして作っておりますので、アメリカ・カナダを参考に外部検証制度をつくっている。
とした。
しかし、上述の通りこれら研究機関の利害関係者であり、外部検証は仕事だ。アメリカのような利害関係者ではない行政が検証するシステムとは質が全く異なる。
3R遵守すらも、気分的に嫌!これが本音か。
3Rが義務化されるとどんな不都合があるのかいまいち想像ができない、最後に山中教授の言葉が挙げられていますが、自分自身の研究に悪影響が出ると言われているんですが、義務化がされるとどういう点で悪影響が出るのかという質問に対して、下田氏はしどろもどろに
2006年体制で2Rについては配慮事項として皆さん動いているときに、「我々としては法規制で強化される、気分的にはやはりやりにくくなる、ということで悪影響ということになると思います」と回答した。
2Rを鋭意取り組んでいるのであれば、「できるかぎり」という言葉まで入っている中、なんの不都合があるのかと不思議に思っていたが、気分的にということなのだから、これは感情論だし、これでは単なるわがままだ。
加えて久野氏は
なぜいけないのかという強い理由ではないかもしれないが、「科学上の利用の目的を達することができる範囲において」という言葉があるが、「その判断を誰がするか、人によって違う可能性がある、そうすると必要ではないところでそういう議論をしなくてはならないそういう可能性がある」とし、「それはもしかしたら科学の発展とかに悪影響を与える」と久野氏自身が懸念していると付け加えた。
しかし、そもそも議論無しで、全て良しとすることが前提となっているからこそ出てくる懸念であり、今現在、この2Rが機能していないということを明らかにしているようなものだ。
登録制度は一切ないのに登録していると主張・・・
小宮山議員から災害時にトラブルが合ったときの対応ができない旨を指摘されると、文部科学省はそのような報告はなかったということを良かったこととして回答した。しかし、そもそも報告義務はなく、何かあっても文科省に報告義務もなければ、報告するシステムもない。あの震災で何も起きなかったとは考えにくい中、何も報告がなかったから安心だと考えるのは、お気楽としか言いようがない。
さらに、下田氏は、犬は狂犬病予防法に基づいて登録が有るし、牛山羊豚は家畜保健衛生所に届けてあり、ニホンザルは特定動物なので都道府県に届けてある、(タイワンザルも特定外来生物として許可が必要)と述べた。災害時に狂犬病予防の登録(一般のペットと同じ登録)と、伝染病予防法による数のみの届け出がなにか役に立つと想像できる人がいるだろうか。畜産場の豚は逃げ出してもリスクは少ないが、なにか病気に感染させられているかもしれない実験に使用された豚が逃げ出せばリスクは高く、しかも見た目ではそのリスクはわからない。犬に至っては、一般のペットに混じって保護され、どこかの家に里親に行くかもしれない。
更に下田氏は
マウスラットは危険性があまりない
と述べる。犬や豚が逃げ出せば捕まえることもでき、また隠れても隠れきれないだろうが、マウスやラットは違う。どこにでも入り込み、穴をほり、あっという間に見失い、環境に溶け込んでいく。その小ささゆえに、人間の目をかいくぐり、実験所からもっとも逃げ出す可能性が高い動物がマウスであることも間違いがないだろう。しかも最も数が多い。
そして、そもそもネコは?うさぎは?マーモセットは?その他の動物は?
それでも下田氏は「現状でも全く問題がない」と言い切る。しかしそれはいくらなんでも苦しい。
全てではないのに全てと言い張る
環境省の実験動物の基準が守られているかどうかは、どのように環境省で確認しているのかという質問に対して、環境省は「基本的に基準自体が守られているかどうかを直接的に確認する法的仕組みはない」と断言した。
その仕組みを補完するために実験動物医学会が外部検証を行っているということなのだが、その対象機関の408機関というのが日本にある動物実験施設全体の数かと質問されると、実験動物医学会は「ほとんどすべてだ」となんども繰り返した。実際には文部科学省が管轄する学校機関のみであるし、ガイドラインを持つ厚生労働省や農林水産省を含めてもそのどこにも管轄されず、完全に無法地帯になっている実験施設もある。
さらに408機関の対象の中で、外部検証を受けたのは52%、213機関にとどまっている。大規模施設は全部だと述べているが、大規模施設よりも小規模施設でこそ、技術や知識不足、方遵守の意識の希薄さや、費用や人材の不足により虐待的飼育や3Rを守らないことが起きうる。
むしろ大規模施設にとっては、動物取扱業の登録が行われてもなんら今と変わりはないという可能性のほうが高い。法規制のメリットは例外がなくなるということなのだ。
アメリカを見習ったのは都合のいい部分だけ
アメリカを見習ったにもかかわらず、登録性については見習わないのはなぜかと聞かれると、下田氏は、アメリカもマウス・ラットなどは登録の必要はなくウサギ以上の動物の登録性があるため日本と同じだと回答した。上述の通り、ネコは?ウサギは?そして狂犬病予防目的や、伝染病予防目的の登録や届け出と、実験動物福祉目的の登録ではまったく異なるという点は無視した状態であった。
3R推進に、一体何の問題があるのか・・・。
骨子に入った部分はたったのこれだけだ。
第五 その他
二 動物の科学上の利用の減少に向けた取組の強化
動物を教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供する場合には、科学上の利用の目的を達することができる範囲において、できる限り動物を供する方法に代わり得るものを利用し、及びできる限りその利用に供される動物の数を少なくすること等により動物を適切に利用しなければならないこと。
答えは文部科学省が持っていた。文科省は、義務化をすることで数を増やせなくなるのであれば本末転倒だ、動物実験の数を減らすことが大事なのではない、と発言した。
動物実験の3Rは
-
Replacement
動物を使用しない実験方法への代替(日本は現行法では配慮事項) -
Reduction
実験動物数の削減(日本は現行法では配慮事項) -
Refinement
実験動物の苦痛の軽減(日本でも義務)
であるが、この理念が世界共通になっている。法的、倫理的、科学的観点から重要であり、犠牲数を減らし、人道的な方法に切り替え、動物実験が持つ科学的なデメリットもなくしていくことが目的である。文部科学省は、代替削減をしながら増やしたいときには増やすと混乱を招く発言をしている。つまり、動物実験を増やしたい、または2Rには賛同していないのだ。つまり、配慮事項は守ることができていないのだ。
はたして世界の中で日本以外に、動物実験を自由に増やすために3Rを推進すると解釈する国があるのか。
代替法がすでにあるものも、動物実験でやりたいと思えば、または自身に技術がなければ動物実験を選択する自由がほしいというのは、3Rの原則に逆行するもので、3Rを重視し遵守しようとしているとは言えない。
規制強化は必要であろうことがやり取りからわかります。しかし、力でねじ伏せられ正しい選択がなされない可能性が高いでしょう。